こんにちは、私は精神科で管理栄養士をしています。
精神科の病気について、管理栄養士の目線で解説しています。
今回のテーマは「ストレス関連障害」です。
うつ病や不安障害の影に隠れていますが、実はかなり多いのがこのタイプ。
職場の人間関係、子育て、受験、引っ越し…「私もそれあるかも」と思う人、意外と多いのではないでしょうか。
「ストレスが原因で心が限界をこえた」そんなときに起きる障害
ストレス関連障害とは
「ものすごく大きなストレスがあって、それが原因で心と体が不調になった」
1. ICD-10(WHO 国際疾病分類)
「ストレス関連障害(F43)」とは、
「例外的または非常に強いストレスに対する反応であり、症状は通常、ストレス因子への曝露後に短期間で出現する。」
(出典:WHO ICD-10 精神および行動の障害 診断ガイドライン)
2. DSM-5(アメリカ精神医学会)
適応障害は「認識可能なストレス因に対する感情的または行動的症状が生じ、それが日常生活に著しい障害をもたらす」
(出典:DSM-5 精神疾患の診断と統計マニュアル)
ストレスって、適度なら必要なものなのです。
仕事の締切、試験、人前に出る緊張。
でも、それが強すぎたり、長すぎたり、突然だったりすると、心が「もうムリ!」ってなって壊れます。
こんな症状が出ることがあります
- 夜眠れない、寝てもすぐ目が覚める
- イライラしたり、泣きたくなったり
- 集中できない、やる気が出ない
- 食欲がガタガタ(食べすぎ・食べられない)
- フラッシュバック(思い出したくないのに思い出す)
代表的なストレス関連障害
① 適応障害
ストレスの原因が「ハッキリ」してるのがポイント。
たとえば…
- 転職して人間関係がきつすぎた
- 子どもが不登校になった
- 親の介護が急に始まった
→ そのストレスにうまく「適応」できず、心と体がダウン。
② PTSD(心的外傷後ストレス障害)
命の危険を感じるほどの出来事がきっかけが多いです。
- 大きな事故
- 災害(地震や火事)
- 暴力や虐待
そんな体験のあと、「何もしてないのに急に思い出す(フラッシュバック)」
「心が過敏になる(ちょっとした音にビクッとする)」
「何も感じられない(感情がなくなる)」
といったことが続きます。
人によっては、何十年も症状が続くこともある、厄介です。
管理栄養士としての私の出番
「ストレスで心が壊れた人と、食事なんて関係あるの?」
って思いますよね。実は、めちゃくちゃ関係あります。
🍴 食べすぎる人
「なんかずっと食べてる…」「夜中にお菓子が止まらない」
→ ストレス食いは人間の本能。無理もない。
でも、動けてないのに食べすぎると、どんどん体重が増える。
「太ってまたストレス…」という負のループに。
🍴 食べられない人
逆に、ストレスで何も食べられなくなる人もいます。
こういう人に「もっと食べなきゃダメでしょ!」なんて言っても逆効果。
→ 私は「いつなら少し食べられそう?」「どんなものなら口に入る?」って聞くようにしてます。
うまく付き合うには
この病気の治療法は、
- 薬(抗うつ薬・抗不安薬など)
- 認知行動療法(ストレスとの向き合い方を変えるカウンセリング)
が主流です。
でも、周りの理解や、寄り添いの姿勢も大切。
栄養指導では、説教よりも「話を聴く」ことに全力を注いでます。
まとめ
- ストレス関連障害は、「心の許容量をこえた」ことで起きる病気
- 急にガタッとくることもあるし、じわじわ壊れていくこともある
- 管理栄養士としても、心と体の両面からサポートしています
この記事を読んで、「あ、自分もそうかも…」と思った人がいたら、
まずは「今の自分の状態」を見つめ直してみてください。
「気合で乗り切れ」は、昭和です。
自分の頑張りが足りなくない、などということは思わないで。
私たちがサポートします。
今は「自分を守ること」が最優先しましょう。
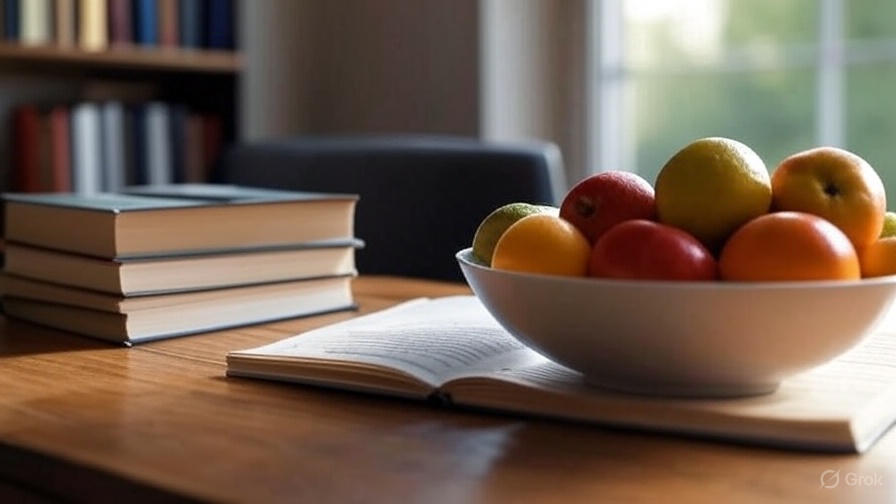


コメント