あなたは、頭痛や吐き気、強い疲労感など、つらい症状が続いているのに、病院で「異常なし」と言われたことはありませんか?
また、「記憶がとんでいる」「自分が自分でないように感じる」そんな感覚に悩んだことは?
今回は、検査では原因が見つからない心と体の不調、「身体表現性障害」と「解離性障害」について、わかりやすく解説します。
身体表現性障害とは?
身体表現性障害とは、頭痛・吐き気・下痢・便秘・疲労感・しびれなど、身体にさまざまな症状が出ているにもかかわらず、検査をしても身体的な異常が見つからない状態を指します。
その原因の多くは、ストレスやトラウマ(心的外傷)によるもので、感情をつかさどる脳のネットワークが乱れることにより、身体に症状が出ると考えられています。
• 痛み
• 動悸
• 息苦しさ
• 発汗
• 手足のふるえ
など、その現れ方は人によって異なります。
解離性障害とは?
解離性障害は、意識・記憶・感情・行動などが「分断」される精神疾患で、ストレス反応のひとつと言われています。
大きなストレスやトラウマがかかると、「自分は苦しくない」「自分は悩んでいないんだ」と自分に暗示をかけます。
その結果、悩んでいる自分と、悩んでいない自分に、自分を分割してしまいます。
体と心のコントロールがつかない。
子供が緊張しておなかが痛い、気持ち悪いが身体表現性障害
子供が緊張して立てなくなったり、歩けなくなったり、声を出せなくなったり、熱が出るのが解離性障害
アルコール依存症の患者さんで、自分が解離性障害だから、知らないうちにコンビニにアルコールを買いに行って飲んでしまう、
この場合は、詐病だとすべての職員が思う。
症状
- 特定の記憶が抜け落ちる(解離性健忘)
- 手や足が動かなくなる・目が見えなくなる・おなかが痛くなる(身体症状症)
- 突然失踪してしまう(解離性遁走)
- 現実感がなくなる感覚(離人感・体外離脱体験)
- 自分以外の人格が現れる(解離性同一性障害、多重人格)
- 狐がとりついた、悪魔が乗り移った感じになる(急性解離反応)
わざとやっているわけではなく、追い詰められてしまった結果、こうなるのです。
本人だけでなく、周囲の人にも理解されにくいことが多く、治療の開始が遅れることもしばしばあります。
身体表現性障害 解離性障害の共通点と違い
じゃあ、何が違うの?
ですが、
表現性障害は自分に苦しみが残ります。
例としては、おなかが痛いとか。
解離性障害は自分の意識はどこかにやっているので痛みが残りません。
実際、精神科医がどうやって診断を付けているかとすると、
精神科・メンタルクリニックのホームページなどを比較すると
人によって違います。
要するにまあ、精神科医の主観でどっちに行くか決まることが多いです。
精神科の疾患は、白黒つけられないからですね。
この辺はすごく難しくて、A先生hが身体表現障害と言っていてもB先生は解離性障害だろうと診断を付けたりします。
じゃあ、診断名が違うことでなにか不具合があるのかというと、
治療方針は変わりません。
患者さん本人が、病名が知りたい、という好奇心にこたえられるかどうかです。
治療の基本
どちらの疾患でも、まず重要なのは正確な診断と丁寧な問診です。特に以下のようなポイントが大切です。
• いつから・どんな症状が出ているか
• 生活背景やストレス要因、過去の病歴などの把握
• 必要な検査で身体疾患を除外する
• 患者本人と家族へのわかりやすい説明
治療の中心は、精神療法(カウンセリングなど)やストレス対処です。薬は補助的に使われます。
ストレスの原因を探っていきます。
たとえば、学校でいじめにあっているのが耐え難いので、
分離した痛みを、一回戻すこと。
もう一回自分の苦しみを受け入れないといけません。
頑張って分けたものをまた戻すので本人はめちゃくちゃ苦しい。
カウンセリングやサポートを入れる、仲間を作るなどして、同じ状況に戻らないようにする。
虐待があったら、児童相談所に通報がいきます。
また、医師だけでなく、心理士・看護師・ソーシャルワーカーなど多職種の連携によるチーム医療が望まれます。
身体表現性障害と「食事」の関係
身体表現性障害では、次のような消化器症状がよく見られます。
• 吐き気
• 嘔吐
• お腹の張り(腹部膨満感)
• 下痢や便秘
ただし、これらの症状があるからといって、必ずしも「食事そのもの」が原因とは限りません。
むしろ、ストレスや心理的要因で胃腸が過敏に反応している可能性があります。
栄養面での注意点
• バランスのとれた食事(特にDHAを多く含む青魚など)は、体調管理や再発予防に役立ちます。
• 一方で、極端なダイエットや偏食は、筋力低下や摂食障害を招き、症状悪化のリスクがあります。
• 食物アレルギーなどの身体疾患が併存している場合は、心身両面からの評価とケアが必要です。
意外と、入院したら普通に食べられる、という人も一定数います。
解離性障害と「食事」の関係
解離性障害と食事に直接的な関連はあまり見られません。
ただし、極端なストレスや摂食障害の併発がある場合には、注意が必要です。
たとえば、
• 拒食や過食による栄養不良
• 食事中のフラッシュバックや解離症状
といったケースでは、食事のサポートや環境調整が重要になることもあります。
おわりに
身体表現性障害も解離性障害も、「甘えている」と誤解されたり、理解されにくい病気です。
しかし、症状は確かに存在し、本人にとっては非常に苦しいものです。
正しい知識を持ち、適切な支援と理解の輪が広がることで、本人も周囲も少しずつ前に進むことができます。
「目に見えないつらさ」への理解が、心を軽くする第一歩になるかもしれません。
一緒に頑張っていけたらいいなと思います。
この記事は精神科医監修の元作っています
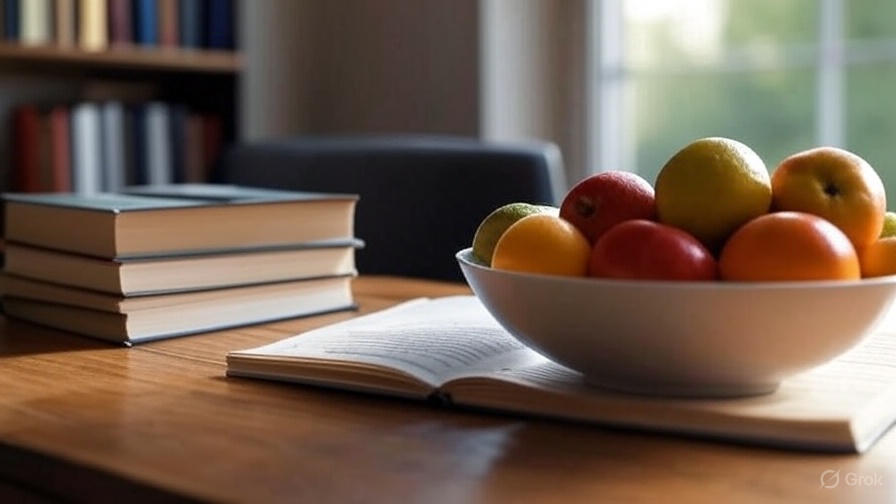

コメント