私は精神科で働く管理栄養士です。
この記事は、
✔ なんとなく毎日が不安でたまらない
✔ 精神科って聞くだけで怖い
✔ 子どもがメンタルの不調を訴えているけど、どうしたらいいかわからない
そんな方に向けて書いています。
実は、精神科でよく見られる「不安障害」について、あまり正確に知られていないことが多いです。
「不安があるのは普通でしょ」「心が弱いだけじゃないの?」そんな誤解がある中で、日常生活に支障が出るほど苦しんでいる人たちがいます。
精神科の病気というと、統合失調症やうつ病はよく知られていますが、
今回は「不安障害」を取り上げます。
「メンタルクリニック(精神科)」がみる病気のきまり
精神科の診療対象はこんなにたくさんあります。
- 統合失調症
- 気分(感情)障害
(以上の2つはその1で書いてるから、↓を見てくれると嬉しいです。)
- 不安障害・神経症性障害
- ストレス関連障害・適応障害
- 身体表現性障害・解離性障害
- 身体症状症、解離性障害
- 摂食障害
- 睡眠障害
- 依存症
- 発達障害
- 人格障害
- 認知症
などなど。
今回はこの中でも「不安障害」についてわかりやすく説明します。
・不安障害って何?
不安とは
「不安」って、誰にでもある普通の感情。危険を察知して自分を守るための自然な反応です。
「不安」はヒトならば、あって当たり前。
不安は、危険やストレスで、自己防衛や準備行動を促すための自然な感情。
「不安を感じない」のは、
「通常なら不安を感じる場面でも緊張や不安を感じない」「リスクや危機を認識しない」などの状態。
リラックスしているときに不安がないのは説明がつきますよね。
危険な状況に身を置かれたときに、本当に「ない」っていうヒトはいないけれど、もし仮にいたなら、きっと狩猟時代なら真っ先にやられるよ。
不安障害とは
でも、それが強すぎて日常生活や仕事、学校に支障が出ると「不安障害」という病気になります。
例えば、
「家の鍵を閉めたか忘れてるかも」と思って、ちょっと戻って確認するのは普通。
でもこれを10回以上繰り返して遅刻してしまうのは、もう普通じゃないってことです。
ここで大事なのは
「日常生活や社会生活に支障が出てしまう」
ってことです。
だから、「不安障害かもしれない」と心配してるなら、胸に手を当てて考えてみてほしい。
「日常生活に支障があるか?」を。
なければ、あなたは普通だ。安心しよう。
この病気は、さっきから言ってるとおり、日常生活に支障がある。ことが病気なのです。
普通なら気にならないことや、危険や危機でないことにも強い不安を感じる。
という特徴があります。
不安障害の症状について
• 身体症状:
頭痛、めまい、動悸、吐き気、下痢、発汗、筋肉の緊張
• 精神症状:
落ち着きがなくなる、イライラする、疲れやすい、集中力低下など。
不安障害にはどんな種類があるの?
いくつか分類分けされているけれど、分類を分けているだけで根本にあるものは同じです。
根本は
不安。
じゃあ、ここから解説していきます。
全般性不安障害(GAD)
常に「何かが不安」。
さまざまな出来事や活動に対して過剰な不安や心配を持つ。
毎日就職とか入試の面接前の緊張とか、結構酷いことやらかしてバレたらどうしようとかの時、不安になりますよね。でもその不安は終われば安心すると思うのですが、この病気の人は、そんなに大きな理由もなく何度も襲ってくる。
周りからしたら、「そんなこと?」、って思うレベルでも。
「そんなことないよ、気にしすぎだよ、気にしなくてもいいよ」って思うけどそんなの本人にしたら本人にしたら死活問題です。
脳がそう思っちゃう病気。
•社会不安障害(社交不安症)
昔は「対人恐怖症」や「あがり症」と言ってたけど、不安障害の一つとされました。
他人から注目される場面や人前で何かをする場面で、強い不安や恐怖を感じてしまいます。
さっきの例の就職や入試の面接はの前なんか、普通に緊張するのは当たり前。
そんな当たり前のことじゃなくて、
人前で話す、字を書く、食事をするといった状況で「恥をかくのではないか」「失敗してしまうのではないか」と心配し、
顔が赤くなったり、手が震えたりとか、汗が異常に出たりとか身体症状が現れる。
外食なんかとんでもない。
記帳なんかできるわけがない。
電車なんか座ってられない。
教室(職場)になんか座って居られるわけない。
だから、周囲に人がいる場面を避けるようになって、学校や職場に行けなくなるみたいな、
日常生活に支障をきたす
ことがある。
人前に出られなくなるんだから、そりゃそうなりますよね。
ここでもポイントは、日常生活に支障をきたす、ってこと。
パニック障害
突然強い不安や恐怖感が襲い、動悸、息苦しさ、めまい、冷や汗、吐き気、死の恐怖などさまざまな身体・精神症状が現れる発作(パニック発作)が繰り返し起こる病気。
パニック発作は通常、
10分以内にピークに達し、
30分程度で自然に収まる。
発作自体で命を落とすことはない。
だから、電車とかで、いきなり隣の人がなっても放っておけばいいから、安心して。
症状の代表的なのは過呼吸。
過呼吸とは
必要以上に呼吸の深さや回数が増えて、
血液中の二酸化炭素濃度が減る。
二酸化炭素は、
「酸」
です。
漢字の通りなんだけど意外と認識してない人がいるのだよね。
酸が減るから、体内がアルカリ性に傾くことで、息苦しさ・めまい・手足のしびれ・動悸・けいれんなどの症状が現れる。
でも、これも収まるから大丈夫。
救急車はいらない。
ただし、心疾患の区別が難しいため、以下の場合は救急要請を!
・意識障害や痙攣がある
• 胸が痛いと訴えている
• 症状が30分で収まらない
この病気には主に3つの特徴があります。
• パニック発作:突然襲う強い不安や恐怖、身体症状
• 予期不安:また発作が起きるのではないかという不安が常につきまとう
• 広場恐怖症:発作が起きた場所や状況を避けるようになる
不安障害と一緒だけれど、違うところは、
パニック起こすか、起こさないか。
恐怖症
特定の対象や状況、場面に対して過度な恐怖を感じ、そのために日常生活に支障が出る病気。
ここもポイントは日常生活に支障が出る、か。
普通に、誰でも怖いものあるよね?
この病気の人たちは、実際の危険とは釣り合わないほどの恐怖を持つんだ。
動物・昆虫恐怖(クモ、ヘビ、犬とか)
自然環境恐怖(雷、暗闇など)
血液・注射・負傷恐怖
状況恐怖(閉所、飛行機など)
その他(嘔吐、大きな音など)
高所恐怖症を例に出すと、
高層ビルや階段、エスカレーターが怖い。
だから、
仕事にいけない。
社交恐怖症(対人恐怖症)では、人が怖い。
だから「人と会うこと」ができなくなる。
簡単にいうと、
前述の不安障害の不安が恐怖に変わったと思えばいい。
そして、この人たちはあんまり居ない印象。
病院では、調子悪い時、不安が高い、って
言うよ。
私は、病院で初めて不安を形容する言葉って
低い、高いなんだって知った。
不安障害の人は入院するの?
実は、不安障害だけで入院になるケースは少ないです。
なぜなら、「不安で病院に行けない」からです。
また、入院が必要になるのは、不安に伴ううつ状態や統合失調症など、他の精神疾患が絡んでくるとき。
治療って何をするの?
薬物療法と心理療法(認知行動療法など)が基本です。
管理栄養士はどう関わるの?
「不安障害と栄養、関係あるの?」
そう思うかもしれません。でも、実は関係大ありです。
外来通院のこの患者さんたちが栄養指導にくる場合があります。
体がエネルギーを使わない
家から出ずに動かずにいると、
体は省エネモードになります。
また、食べ過ぎ傾向になる人もいます。
薬の影響もあるんだけど。
なので体重減らしましょう目的。
難しいんだ。
カロリーのinもout も減らしましょう、だよ。
まず、
動かなさすぎてそんなに食べる量が変わってないのに体重が増えた
って患者さんもいます。
うつ状態でやる気がなしになっちゃった人に
「散歩どうですか?」とか
「運動しませんか?」
っても言っても、やっぱりできないんだよね。
ストレスで食べ過ぎてしまう人
「もういいよ、それがストレス解消になるなら食べたらいいよ」
って心の中で思いながら、
「●●が食べ過ぎだから、減らしましょうか。できますか?」
って指導しています。
中にはそんなにこだわりがなくて体重もなんか増えた、食事量を減らすのにも全く抵抗ない、って人もいるのでそういった患者さんは、するするっと体重がうまく減ること「も」あります
また、動かないと筋肉量が減るので太りやすい体になっちゃってるし、筋肉量が減ると疲れやすくもなるので、
少しでいいから運動はしてほしいと思います。
外に出るのは大変だから、
テレビ体操とか、youtubeで動画がいいのがいっぱい転がっているから探してみて、とか。
食べられない人
強い不安や、ストレスで、食「欲」そのものが失われている人もいます。
食べられないのに食べてって言うのは辛いし、本人も辛い。
私は、患者さんの話を聞くのが大事だと思っているので、
栄養指導ではなるべく喋らないように、聞く方に徹しています。
そして患者さんからのお話から、
何だったら食べられそう
とか
いつだったら食べられる、
小さな手がかりから、食べる感覚を取り戻してもらえるよう、言葉を選びながら関わっています。
おわりに:精神科と関わる管理栄養士の思い
「精神科に栄養士なんて必要?」
「メンタルの病気に食事って意味あるの?」
そう思われることも、よくあります。
でも、私は信じています。
食事は、その人の「生きる力」につながっていると。
「食べることができた」「ちょっと体を動かせた」
その一歩一歩を支えるのが、私たちの仕事です。
精神科の世界は、まだまだ偏見と誤解が多い場所。
だからこそ、私はこの仕事を通して「見えないつらさ」に光を当てたいと考えます。
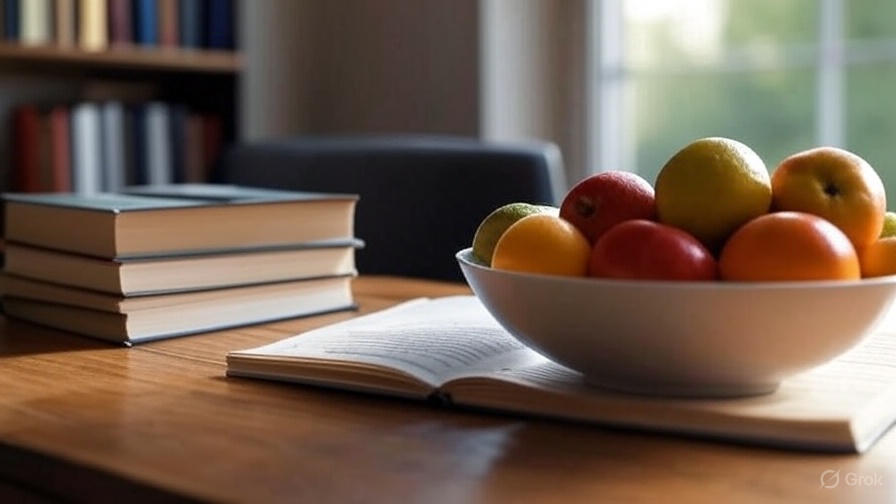

コメント