「精神科」と聞くとちょっと怖い?
精神科という言葉を聞いたとき、どこか“怖い”イメージを抱いたことはありませんか?
例えば、ホラー映画の舞台やゲームに出てくるような廃墟…。
「精神科=怖い」という先入観は、意外と根深いものです。
でも、実際の精神科病棟はそんな怖い場所ではありません。
むしろ、とても人間らしい営みがある場所。私は管理栄養士として精神科病棟で働いてきましたが、その中で見えてきたのは、心の病とともに生きる“人間のリアル”です。
この記事では、精神疾患の中でも特に「統合失調症」と「双極性障害」について、医療の専門職ではない「管理栄養士」の視点から、現場で感じたことをお伝えしていきます。
精神科病院・診療所・クリニックの違い
精神科と一口に言っても、診療の場には種類があります。ざっくり分けると以下の通りです:
- 病院:入院ができる(もちろん通院も可能)
- 診療所:通院がメインだが、小規模の入院施設も併設していることがある
- クリニック:基本的に外来のみ(医院とも呼ばれる)
また、「精神科」という言葉のイメージを避けるため、「心療内科」や「メンタルクリニック」といった名前の医療機関もあります。
ただし、「心療内科」は一般に内科医が精神的な問題にも対応しているというケースが多く、本格的に治療したい方には精神科専門医の受診をおすすめします。
精神科で診る主な病気
精神科で扱う代表的な精神疾患は以下のように分類されます:
- 統合失調症
- 気分(感情)障害(例:うつ病・双極性障害)
- 不安障害・神経症
- ストレス関連障害・適応障害
- 身体表現性障害・解離性障害
- 摂食障害
- 睡眠障害
- 依存症
- 発達障害
- パーソナリティ障害(人格障害)
- 認知症
本記事では、この中から「統合失調症」と「双極性障害(気分障害)」について詳しく解説します。
統合失調症とは?
統合失調症は、幻聴や妄想などの症状が現れる精神疾患です。
たとえば、「誰かに悪口を言われている」「誰かに命を狙われている」といった妄想を強く信じてしまうため、周囲に対して攻撃的になることもあります。
幻聴・幻視とは?
幻聴は、統合失調症の特徴的な症状のひとつ。実際には存在しない「声」が聞こえ、それに反応して独り言を言ったり、大声で叫んだりすることがあります。
幻視(見えないものが見える)については、アルコール依存症や認知症、一部の薬の副作用などでも見られることがあります。
周囲から見れば“意味不明”な行動でも、本人にとっては「本当に聞こえている」「見えている」現実なのです。
統合失調症の偏見と現実
「統合失調症の人は暴れる」といったイメージがありますが、それはごく一部のケースに過ぎません。
実際には、じっとしていて口数が少ない方のほうが多い印象です。むしろ、他人を傷つけるのは健常者の方が多いとも言われています。
さらに、統合失調症の方の多くは自殺リスクが高いという事実は、あまり知られていません。
ただし、現在は良い薬も増え、適切な治療を受ければ一般の人とほとんど変わらない生活が可能です。
なぜ長期入院になるのか
統合失調症は、幻聴や妄想によって生活力が極端に落ちてしまう人も多く、
電気・ガス・水道が止まってもそのまま過ごしてしまったり、住まいを失って路上生活になったりといったケースもあります。
また、家族関係の希薄さや孤立も問題のひとつ。退院に対して家族が拒否するケースも少なくありません。
こうした背景から、長期入院が必要な人が多くなるのが現実です。
グループホームや作業所とは?
退院後に地域で暮らすためには、以下のような支援施設が用意されています:
- グループホーム:生活支援を受けながら地域で暮らす場
- 作業所:日中に通って作業を行う施設(チラシ折り、農作業、クラフト制作など)
就労支援には以下の種類があります:
- 就労移行支援:一般就労を目指すトレーニング
- 就労継続支援A型:雇用契約あり、最低賃金が保障される
- 就労継続支援B型:雇用契約なし、平均工賃は令和4年で約243円
- 就労定着支援:就職後の生活・仕事の支援
B型作業所に通う人が多い印象ですが、賃金の低さから「行っても意味がない」と感じてしまう方もいます。
しかし大切なのは、お金ではなく「人間らしさ」や「社会とのつながり」を取り戻すことだと思います。
双極性障害(躁うつ病)とは?
双極性障害は、気分の振れ幅が極端に大きいことが特徴です。
- 躁状態:異常に元気になり、活動的になりすぎてしまう
- 軽躁状態:躁状態より軽度だが、普段より明るくテンションが高くなる
- うつ状態:無気力、無関心、睡眠障害や食欲不振が現れる
一番問題なのは「躁状態」
躁状態になると、自分が無敵だと思い込み、高額な買い物、ギャンブル、大きな借金など、周囲を巻き込むトラブルを引き起こすことがあります。
病気の影響とはいえ、経済的な責任は免除されるわけではなく、多くの場合、家族が負担を背負うことになります。
精神科で管理栄養士ができること
意外かもしれませんが、精神疾患のある方にとって栄養管理はとても重要です。
薬の副作用による体重増加
抗精神病薬や抗うつ薬の中には、**体重が増えやすい薬(例:オランザピン、クエチアピン)**があります。
糖尿病が併発すると、薬が使えなくなる可能性もあるため、生活習慣病の予防として栄養指導が必要になります。
痩せすぎ・低栄養
- 統合失調症:セルフケアが難しく、食事を摂れずに痩せてしまう
- 躁状態:活動過多により、食事を忘れて体重が減る
このような場合、エネルギーの補給や栄養状態の改善を目的とした関わりが必要になります。
まとめ:精神科は“怖い”場所じゃない
精神科の病気は誰にでも起こり得るものです。
そして、患者さん自身が最も苦しんでいるということを忘れてはいけません。
精神疾患をもつ方々が、安心して地域で暮らしていくためには、正しい知識と理解、そして支える社会の仕組みが必要です。
管理栄養士という立場から、精神科の患者さんと日々関わっているからこそ見えてくるリアル。
この記事が、精神科の世界を少しでも身近に感じていただくきっかけになれば幸いです。
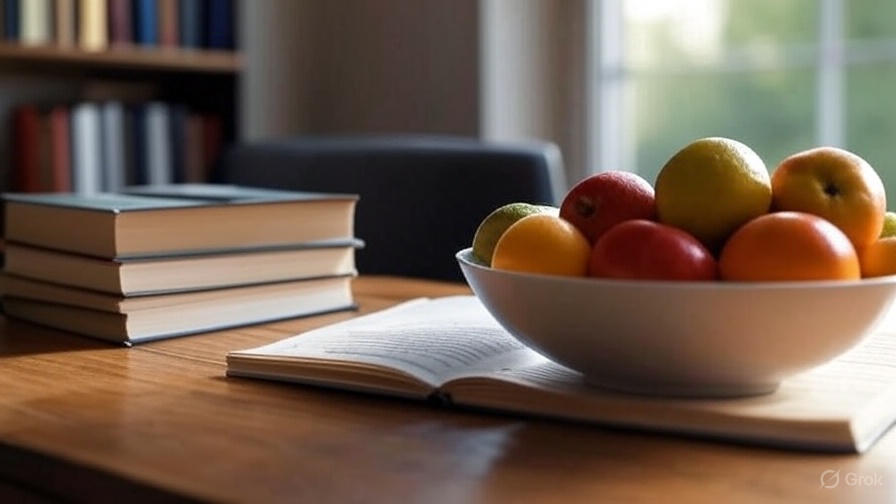


コメント